スティーヴ・レイシーが1965年に30歳で米国を離れるまでに正式録音したレコードはたった4枚だったが、ヨーロッパに移住後の30年余に、合計で150枚を超えるレコード数に膨らんだ。晩年多作になったのはリー・コニッツも同じで、またそれらレコーディングの大多数はヨーロッパ吹き込みという点も同じだ。レイシーもコニッツも、スナップショットのように、その時点における演奏記録をレコードに残し続けることで、自身の音楽の進化を確認する作業を続けた。それを可能にしたのは、大量販売を優先する米国流商業主義とはレコード文化の異なるヨーロッパのインディレーベルの存在で、フランスのSaravahやOwl、イタリアのSoul Note、スイスのHatology(Hat Hut) などのレーベルが、彼らのような先進的アーティストの挑戦と創造意欲を実質的に支えていたと言えるだろう。その時代のレイシーのレコードを紹介できるほどの知識も経験も私にはないが、翻訳中に探して初めて聴いたCDの中から、私なりに印象に残ったものを以下に何枚か挙げてみたい(だが『Scratching…』 を除くと、結局は80年代以降にレイシーが自身のバンドで目指した独自の音楽(art song/lit-jazz) 系よりも、自分好みの雰囲気を持ったジャズ寄りのレコードばかりになってしまったが…)。
 本書#27で書かれているように、『Scratching the Seventies/Dreams』(1997) は、1970年にローマから妻のイレーヌ・エイビと共にパリに移住したレイシーが、フランスのSaravahレーベルから当時リリースした5枚のLPレコードを(20年後にレイシーがレギュラー・セクステットを解散した後に)、同レーベルが再発した3枚組CDだ。ほとんどがレイシー作品からなるその5枚のLPとは、『Roba』(1969)、『Lapis』(1971)、『Scraps』(1974)、『Dreams』(1975)、『The Owl』(1977) であり、『Roba』はイタリア、それ以外はパリ移住後の録音である。『Roba』とソロ『Lapis』以外は、イレーヌ・エイビ(vo, vln)とスティーヴ・ポッツ(as, ss) などによるレギュラーバンドによるもので、詩人ブライオン・ガイシンBrion Gysin (1916- 86)との共作『Dreams』にはデレク・ベイリーがギターで、また『The Owl』には加古隆がピアノで参加している。私が入手したこの3枚組CDには立派なブックレットが入っているが、それが本書#27のエチエンヌ・ブリュネによるインタビュー(1996) のオリジナル・フランス語版だ。その中で、これらのレコードで演奏している各曲の内容、意図、背景について、レイシー自身が詳しく解説している(レイシーの音楽思想を知る上で、非常に興味深いコメントが聞ける)。
本書#27で書かれているように、『Scratching the Seventies/Dreams』(1997) は、1970年にローマから妻のイレーヌ・エイビと共にパリに移住したレイシーが、フランスのSaravahレーベルから当時リリースした5枚のLPレコードを(20年後にレイシーがレギュラー・セクステットを解散した後に)、同レーベルが再発した3枚組CDだ。ほとんどがレイシー作品からなるその5枚のLPとは、『Roba』(1969)、『Lapis』(1971)、『Scraps』(1974)、『Dreams』(1975)、『The Owl』(1977) であり、『Roba』はイタリア、それ以外はパリ移住後の録音である。『Roba』とソロ『Lapis』以外は、イレーヌ・エイビ(vo, vln)とスティーヴ・ポッツ(as, ss) などによるレギュラーバンドによるもので、詩人ブライオン・ガイシンBrion Gysin (1916- 86)との共作『Dreams』にはデレク・ベイリーがギターで、また『The Owl』には加古隆がピアノで参加している。私が入手したこの3枚組CDには立派なブックレットが入っているが、それが本書#27のエチエンヌ・ブリュネによるインタビュー(1996) のオリジナル・フランス語版だ。その中で、これらのレコードで演奏している各曲の内容、意図、背景について、レイシー自身が詳しく解説している(レイシーの音楽思想を知る上で、非常に興味深いコメントが聞ける)。
これらは、いずれも60年代フリー・ジャズを通過した後の音楽(post-free)を追及していた時代の作品で、中でも間章も気に入ったソロ『Lapis』(1971)は評価の高いレコードだった。レイシー的には、1975年のブライオン・ガイシンとの共作『Dreams』が、その時代の最高作だったと言っている。このCD版のタイトル “scratching” とは、いろいろな意味のある英語で、DJ用語にあるように基本は「引っ掻く」という意味だが、「苦労して金をかき集める」とか「何とか生計をたてる」という意味もあって、1970年代前半のパリで、レイシーが新たな音楽を模索して苦闘していた時代を象徴する言葉なのだ。半世紀前のこうした実験的音楽を鑑賞し、楽しむセンスは残念ながら今の私にはないが、本書を読みながらじっくりと聴いてみると、あの混沌としつつも活力が満ちていた時代に、ヨーロッパの片隅で彼らが創造しようとしていた音楽と、その挑戦を支えていた気概や精神は確かに伝わってくる。
 1975年に初来日したレイシーは、招聘した間章のプロデュースで富樫雅彦、吉沢元治、佐藤允彦たちと国内のコンサート・ツアーを行い、何枚か録音を残した(『Stalks』他)。特に、事故で下半身の動きは失ったものの、当時は復帰して本格的活動を再開し、『Spiritual Nature』等の新作が好評だった富樫雅彦(1940-2007) との、その後も続いた音楽的交流は本書に書かれている通りだ。1979年にパリに渡って公演し、ドン・チェリーや加古隆たちと現地録音した富樫が、1981年にレイシーと日本で録音したキング盤『Spiritual Moments』(富樫作の3曲とレイシー作2曲) では、当時レイシー・バンドにいたケント・カーター(b)とのトリオによる研ぎ澄まされた演奏が聴ける。モンク伝来の「余計なものは削ぎ落とす」ことを信条とし、スペースを重視するレイシーの美意識と、少ない音数で見事に空間を造形する富樫のパーカッションは、基本的に音楽的相性が良いのだと思う。3人で並んで写っているジャケット写真も貴重で、楽しそうな雰囲気が印象に残る。1986年にはレイシー、ケント・カーターにドン・チェリー(tp) も加わった『Bura Bura』 、1991年にはレイシー、富樫のデュオ『Eternal Duo』、その後も2000年には深谷エッグファームでレイシー、富樫に高橋悠治(p)というトリオでも録音するなど、2004年にレイシーが亡くなるまで交流は続き、その間二人は数多くの貴重な録音を残した。
1975年に初来日したレイシーは、招聘した間章のプロデュースで富樫雅彦、吉沢元治、佐藤允彦たちと国内のコンサート・ツアーを行い、何枚か録音を残した(『Stalks』他)。特に、事故で下半身の動きは失ったものの、当時は復帰して本格的活動を再開し、『Spiritual Nature』等の新作が好評だった富樫雅彦(1940-2007) との、その後も続いた音楽的交流は本書に書かれている通りだ。1979年にパリに渡って公演し、ドン・チェリーや加古隆たちと現地録音した富樫が、1981年にレイシーと日本で録音したキング盤『Spiritual Moments』(富樫作の3曲とレイシー作2曲) では、当時レイシー・バンドにいたケント・カーター(b)とのトリオによる研ぎ澄まされた演奏が聴ける。モンク伝来の「余計なものは削ぎ落とす」ことを信条とし、スペースを重視するレイシーの美意識と、少ない音数で見事に空間を造形する富樫のパーカッションは、基本的に音楽的相性が良いのだと思う。3人で並んで写っているジャケット写真も貴重で、楽しそうな雰囲気が印象に残る。1986年にはレイシー、ケント・カーターにドン・チェリー(tp) も加わった『Bura Bura』 、1991年にはレイシー、富樫のデュオ『Eternal Duo』、その後も2000年には深谷エッグファームでレイシー、富樫に高橋悠治(p)というトリオでも録音するなど、2004年にレイシーが亡くなるまで交流は続き、その間二人は数多くの貴重な録音を残した。
 レイシーとピアニストのマル・ウォルドロンMal Waldron(1925-2002)は、50年代半ばから交流があり、1958年のモンク作品集『Reflections』で初共演して以来の盟友ともいえる間柄で、レイシー同様ウォルドロンも60年代半ばにヨーロッパへ移住し、移住後も二人は様々な機会に共演を重ね、特に80年代には数多く共演した。パーカッシブで厚く重い低域を持ったウォルドロンのピアノは、明らかにモンクの影響を感じさせ、またレイシーが言うように、50年代後半のビリー・ホリデイの歌伴時代から伴奏の名人として知られていた。ジャッキー・マクリーンと共にビリー・ホリデイを偲んだ『Left Alone』(1959 Bethlehem) や、ソロ・アルバム『All Alone』(1966 GTA) など、1970年代になると日本でも独特の陰影のあるピアニズムが支持されて人気を博し、何度も来日し、日本人の奥さんと結婚するなど、ジャズ界きっての日本通だった。しかしウォルドロンは、実は当時の日本のジャズファンが抱いていた一般的イメージとは異なる、急進的側面も併せ持ったピアニストでもあった。アムステルダムのコンサートホール (旧) 「Bimhuis」でライヴ録音された二人のデュオ『At the Bimhuis 1982』(Daybreak) は、2006年になって初めてCD化された未発表音源だ。その4年前の1978年に急逝した間章に捧げた曲が冒頭の〈Blues for Aïda〉で、日本通のウォルドロンと、日本文化をリスペクトしていたレイシーの二人による、深い日本的エキゾチスム(尺八風)を感じさせるデュオ演奏が聞ける(清水俊彦氏によれば、『万葉集』の悲歌をモチーフにした曲だという)。ウォルドロンの前衛的自作曲〈Snake Out〉、モンクの代表作3曲(Reflections, Round Midnight, Epistrophy) も含めて、レイシーの美しいソプラノの背後から聞こえる、ウォルドロン節ともいえる低域のリフは、オールド・ジャズファンにはどこか懐かしいサウンドでもある。長い交流を背景にした二人の、ぴたりと息の合った素晴らしいデュオ・アルバムだ。
レイシーとピアニストのマル・ウォルドロンMal Waldron(1925-2002)は、50年代半ばから交流があり、1958年のモンク作品集『Reflections』で初共演して以来の盟友ともいえる間柄で、レイシー同様ウォルドロンも60年代半ばにヨーロッパへ移住し、移住後も二人は様々な機会に共演を重ね、特に80年代には数多く共演した。パーカッシブで厚く重い低域を持ったウォルドロンのピアノは、明らかにモンクの影響を感じさせ、またレイシーが言うように、50年代後半のビリー・ホリデイの歌伴時代から伴奏の名人として知られていた。ジャッキー・マクリーンと共にビリー・ホリデイを偲んだ『Left Alone』(1959 Bethlehem) や、ソロ・アルバム『All Alone』(1966 GTA) など、1970年代になると日本でも独特の陰影のあるピアニズムが支持されて人気を博し、何度も来日し、日本人の奥さんと結婚するなど、ジャズ界きっての日本通だった。しかしウォルドロンは、実は当時の日本のジャズファンが抱いていた一般的イメージとは異なる、急進的側面も併せ持ったピアニストでもあった。アムステルダムのコンサートホール (旧) 「Bimhuis」でライヴ録音された二人のデュオ『At the Bimhuis 1982』(Daybreak) は、2006年になって初めてCD化された未発表音源だ。その4年前の1978年に急逝した間章に捧げた曲が冒頭の〈Blues for Aïda〉で、日本通のウォルドロンと、日本文化をリスペクトしていたレイシーの二人による、深い日本的エキゾチスム(尺八風)を感じさせるデュオ演奏が聞ける(清水俊彦氏によれば、『万葉集』の悲歌をモチーフにした曲だという)。ウォルドロンの前衛的自作曲〈Snake Out〉、モンクの代表作3曲(Reflections, Round Midnight, Epistrophy) も含めて、レイシーの美しいソプラノの背後から聞こえる、ウォルドロン節ともいえる低域のリフは、オールド・ジャズファンにはどこか懐かしいサウンドでもある。長い交流を背景にした二人の、ぴたりと息の合った素晴らしいデュオ・アルバムだ。
 1980年代のレイシーのレコードで、日本のジャズファンにいちばんよく知られているのは、ギル・エヴァンスGil Evans (1912-88) 最後の録音となった、二人のデュオ作品『Paris Blues』(Owl) だろう。1987年12月の本録音の3ヶ月後(88年3月)にエヴァンスは亡くなった。1950年代半ばに『Gil Evans & Ten』で、レイシーとソプラノサックスを実質的にジャズ界にデビューさせた恩人がエヴァンスであり、二人はその後30年にわたって親しく交流を続けていた。二人には共通のサウンド嗜好があったように思えるし、またエヴァンスはレイシーのソプラノ・サウンドを本当に気に入っていたのだろう。ここでは二人の自作曲とエリントン、ミンガスの作品を選び、あまり耳にできないエヴァンスの弾くピアノ(エレピも)演奏が聴ける。二人が歩んできた人生を振り返るように語る、レイシーのソプラノとエヴァンスのピアノのサウンドが空間で美しく溶け合っている。
1980年代のレイシーのレコードで、日本のジャズファンにいちばんよく知られているのは、ギル・エヴァンスGil Evans (1912-88) 最後の録音となった、二人のデュオ作品『Paris Blues』(Owl) だろう。1987年12月の本録音の3ヶ月後(88年3月)にエヴァンスは亡くなった。1950年代半ばに『Gil Evans & Ten』で、レイシーとソプラノサックスを実質的にジャズ界にデビューさせた恩人がエヴァンスであり、二人はその後30年にわたって親しく交流を続けていた。二人には共通のサウンド嗜好があったように思えるし、またエヴァンスはレイシーのソプラノ・サウンドを本当に気に入っていたのだろう。ここでは二人の自作曲とエリントン、ミンガスの作品を選び、あまり耳にできないエヴァンスの弾くピアノ(エレピも)演奏が聴ける。二人が歩んできた人生を振り返るように語る、レイシーのソプラノとエヴァンスのピアノのサウンドが空間で美しく溶け合っている。
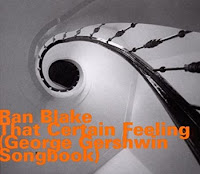 ピアニストで作曲家のラン・ブレイクRan Blake (1935-)は、大学を卒業したばかりの若い時に、自らセロニアス・モンク家に出入りしていたほどモンクとその音楽に傾倒していた。ネリー夫人が忙しいときには、まだ幼かったモンク家の二人の兄妹(TootとBarbara)の面倒を見ていたし、モンクの死後、若くして病気で亡くなったそのBarbaraを追悼するアルバムも制作した。ブレイクはジャズ演奏家であると同時に、サード・ストリームを主導した作曲家ガンサー・シュラーたちとの長い音楽的交流もあり、また教育者としてニューイングランド音楽院で長年教鞭をとってきたインテリでもある。だからスティーヴ・レイシーとの接点も共通点も当然あったことだろう。『That Certain Feeling-George Gershwin Songbook』(1990 Hatology)は、そのブレイクのピアノと、レイシーのソプラノ、リッキー・フォードRicky Ford (1954-) のテナーサックス2管による、ジョージ・ガーシュインの名曲をカバーしたアルバムだ。ソロ、デュオ、トリオと、どの曲も深く沈潜する知的で陰影に満ちた演奏だが、特にレイシーとの『The Man I Love』は、透徹した究極のクールサウンドが実に味わい深い素晴らしいデュオだ。翌年ブレイクは、全曲モンク作品を演奏したピアノ・ソロアルバム『Epistrophy』(1991 Soul Note)をリリースしている。
ピアニストで作曲家のラン・ブレイクRan Blake (1935-)は、大学を卒業したばかりの若い時に、自らセロニアス・モンク家に出入りしていたほどモンクとその音楽に傾倒していた。ネリー夫人が忙しいときには、まだ幼かったモンク家の二人の兄妹(TootとBarbara)の面倒を見ていたし、モンクの死後、若くして病気で亡くなったそのBarbaraを追悼するアルバムも制作した。ブレイクはジャズ演奏家であると同時に、サード・ストリームを主導した作曲家ガンサー・シュラーたちとの長い音楽的交流もあり、また教育者としてニューイングランド音楽院で長年教鞭をとってきたインテリでもある。だからスティーヴ・レイシーとの接点も共通点も当然あったことだろう。『That Certain Feeling-George Gershwin Songbook』(1990 Hatology)は、そのブレイクのピアノと、レイシーのソプラノ、リッキー・フォードRicky Ford (1954-) のテナーサックス2管による、ジョージ・ガーシュインの名曲をカバーしたアルバムだ。ソロ、デュオ、トリオと、どの曲も深く沈潜する知的で陰影に満ちた演奏だが、特にレイシーとの『The Man I Love』は、透徹した究極のクールサウンドが実に味わい深い素晴らしいデュオだ。翌年ブレイクは、全曲モンク作品を演奏したピアノ・ソロアルバム『Epistrophy』(1991 Soul Note)をリリースしている。
最後に、レイシーの共同制作者で1986年に亡くなった詩人のブライオン・ガイシンを追悼すべく、同年12月にパリで行なわれた3日間のコンサートの模様をプライベート録画し、4篇に編集してYouTubeにアップした映像を、著者のJason Weiss氏が送ってきたので、以下にそのリンクをはっておく。いずれも本書に登場するガイシン作品をフィーチャーしたステージだ。レイシーのソプラノ、イレーヌ・エイビの歌、JaosnWeissたちが一緒に歌っている模様、特に#4では踊る大門四郎、アクション・ペインティングをする画家の今村幸生の姿も見られる…など、いずれも貴重な映像記録だ(私にはディープすぎてよくわからない世界だが、1980年代後半の彼らのパフォーマンスに興味ある人はご覧ください)。
Gysin/Lacy#1 "Somebody Special" (Brion Gysin) - Steve Lacy Sextet - Dec 17 1986 - YouTube
Gysin/Lacy#2 "Nowhere Street" (Brion Gysin) - Steve Lacy Sextet - Dec 17th 1986 - YouTube
Gysin/Lacy#3 Cut-Ups -Texts & songs by Brion Gysin from Trois Soirs pour Brion Gysin - 18 Dec 1986 - YouTube
Gysin/Lacy#4 A Japan-ing for Brion Gysin ブリオン・ジシンに捧ぐ日本-ing Musée D'Art Moderne Paris Dec19 1986 - YouTube


