ロリンズと言えば、豪快で男性的なサウンドのテナーサックスで有名だ。スタン・ゲッツのソフトで流麗なサウンドや、コルトレーンの端正で透き通ったテナー・サウンドに比べると、バラード・プレイでもロリンズのサウンドは分厚く、個性的タンギング奏法ゆえに、引っかかりが多いゴツゴツした感触のプレイが多い印象がある。だが一方で、そのサウンドからは他の奏者にはない、深いエモーションと、「物語性」を強く感じさせる濃厚な人間的味わい、歌心がある。そしてポピュラーソングの知識が半端ないので、選曲がユニークで、誰でも知っているような単なるスタンダード曲ではなく、「アメリカン・ソングブック」の隅から引っ張り出してきたような珍しい曲を演奏することが多いのも特長だ。
ロリンズの初リーダー作が、26歳のときの『Sonny Rollins with The Modern Jazz Quartet』(1956 Prestige)で、MJQとの共演4曲(録音1953年)と 、ケニー・ドリュー(p)、パーシー・ヒース(b)、アート・ブレイキー(ds)というトリオ他(1曲マイルスがピアノを弾くという珍品も入っている)との9曲(録音1951年)のセッションを1枚にまとめたコンピアルバムだ。とても20代前半とは思えない、ロリンズの滑らかかつ骨太のワンホーン・テナーが、ミディアム・テンポとスロー・バラードの全編にわたって心地よく響く名盤である。LPが主流になる以前で、全曲3分前後という短さも気持ちよく聞ける理由の一つだ。バラードではMJQとの "In a Sentimental Mood" が実に良い味を出しているが、ケニー・ドリュー・トリオをバックにした"Time on My Hands", "This Love of Mine"という2曲もリラックスして余裕綽々の若きロリンズの歌声が聞こえてくる。「"モダン・ジャズ"というものを聞いてみたい」という人には、真っ先にこのアルバムを勧める。2026/01/28
ジャズ・バラードの森(7)ソニー・ロリンズ
2025/12/24
ジャズ・バラードの森(6)I Get Along Without You Very Well
 |
| ヘル・パラダイス(2018年部分) |
 |
| スケッチング・スカイスクレーパーズ 2025年部分 作家蔵 |
 |
| I Thought About You A Tribute to Chet Baker Eliane Elias (2013) |
 |
| My Ideal A Tribute to Chet Baker Sings Amos Lee (2022) |
2025/09/18
ジャズ・バラードの森(5)Blame It on My Youth
"ブレイム・イット・オン・マイ・ユース Blame It on My Youth"は、1934年に作曲された古いバラード(曲 Oscar Levant、詞 Edward Heyman)。「あれも、これも、若さゆえの……」という歌詞で、タイトル通り、どう訳しても日本語なら『若気の至り』しかないだろう。誰しもそうかもしれないが、思い起こせば私も「若気の至り」が山ほどあって、入りたい穴がいくつあっても足りないくらいだ。しかし、人間若いころは本当にバカなことを言ったり、したりするものだと思う。反省するしかない(もう遅いが)。
 |
| After Midnight (1957) Nat King Cole |
 |
| The Cure (1990) Keith Jarret |
 |
| The Art of the Trio Vol 1 (1997) Brad Mehldau |
 |
| Minor Meeting (2001) Carsten Dahl |
 |
| Pao (2001) Eugene Pao |
2025/07/21
ジャズ・バラードの森(4)Misty
 |
| Misty 山本剛 (1974) |
.jfif) |
| The Original Misty Errol Garner (1954) |
 |
| Vaughan and Violins Sarah Vaughan (1959) |
 |
| Smokin' at the Half Note Wes Montgomery (1964) |
 |
| Flamingo S.Grappelli & M.Petrucciani (1995) |
2025/06/29
ジャズ・バラードの森(3)For All We Know
"フォー・オール・ウィ・ノウ For All We Know" は、1934年に書かれた古い曲で (J. Fred Coots曲/ Sam M. Lewis詞)、短く、どちらかと言えば歌詞もメロディも地味だが、別れゆく男女の、やむにやまれぬ切ない気持ちが込められた非常に美しいラヴソングである(70年代にカーペンターズが唄ったのは同名異曲)。だが単に陳腐でセンチメンタルな恋歌ではなく、曲に品格があり、いかにもアメリカン・バラード的な温かさ、やさしさが歌詞とメロディ全体から伝わってくる名曲だ。だから唄い上げるよりも、哀切さと共に、歌の底に流れる、相手を思いやるやさしさが、さりげなく表現されている穏やかな歌唱や演奏が曲想に合っていると思う。『Lady in Satin』(1958) のビリー・ホリデイBillie Holiday の歌唱はこの点でまさに完璧だ。
 |
| Lady in Satin Billie Holiday (1958) |
私有の女性ジャズ・ヴォーカルでは、ニーナ・シモン (1957)、とドーリー・ベイカー(1993)があるし、男声ではナット・キング・コール (1958) も有名だ。しかし上述した理由から、ゴスペル調でドラマチックに唄い上げるニーナ・シモンや、高らかな美声のナット・キング・コールよりも、最晩年(亡くなる前年)、人生を知り尽くし、彼岸に向かって歩き始めたかのように、ストリングスをバックに仄かな暗さを湛えて唄う『Lady in Satin』のビリー・ホリデイの枯れた歌唱が、私的にはやはりいちばん心に響く。声や技術の衰えとか、年齢による歌唱の質の問題はあるだろうが、そんなことなど超越した、歌に込めた情感の素晴らしさがこのアルバムのホリデイにはある(それは、バド・パウエルやモンクといったジャズの巨人たちの、最晩年の演奏にも感じることだ。)"I'm a Fool to Want You" をはじめ、 ホリデイのこのレコードは全曲が素晴らしいが、特にこの曲は短く、シンプルで、美しいがゆえに、なおさらだ。
 |
| The Art of the Trio Vol.3 Brad Mehldau (1998) |
.jpg) |
| Jasmine Keith Jarret & Charlie Haden(2010) |
 |
| Guitar On the Go Wes Montgomery (1961) |
 |
| Live in Tokyo Chet Baker (1987 King) |
2025/05/31
ジャズ・バラードの森 (2)Soultrane
 |
| Mating Call Dameron/Coltrane (1957 Prestige) |
 |
| Plays Tadd Dameron Barry Harris (1975 Xanadu) |
 |
| Gentle November Kazunori Takeda (1979 Frasco) |
 |
| Playin' Plain Koichi Hiroki (1996 Biyuya) |
2025/04/30
ジャズ・バラードの森(1)Spring Can Really Hang You Up the Most
 |
| Clap Hands, Here Comes Charlie! Ella Fitzgerald (1961 Verve) |
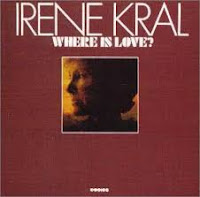 |
| Where is Love? Irene Kral (1975 Choice) |
 |
| Pop Pop Rickie Lee Jones (1991 Geffen) |
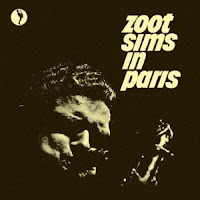 |
| Zoot Sims in Paris (1961 UA) |
2025/03/27
ジャズ・バラードの森を歩く
去年の11月14日に「こころ旅」の火野正平氏がぽっくりと逝ってしまい、12月7日の追悼記事の後3ヶ月以上このブログの更新もしていなかった。ひょっとして私もぽっくり逝ったか…?と思った人もいるかもしれないが、安心してください。生きてますから。ただし腰痛が続いていて、そこは正平氏と同じだし、もういつ逝っても不思議ではない歳になった。
ここ数ヶ月間ソニー・ロリンズの伝記『Saxophone Colossus』翻訳の仕上げ作業に集中していたのでブログ更新の時間がなかった。前回の正平氏の記事がちょうど200番目になり、キリもいいし、ジャズネタもそろそろ尽きてきたので、もうこのへんでブログも店終いしようかとも思っていた。だが、翻訳がやっと2月でほぼ完了し、多少余裕ができたこともあって、やはりブログも再開してみることにした。NHK-BSの「こころ旅」も、今年の春の旅が、私的ないちオシだった田中美佐子氏に決まり、4月から放映開始するそうだ。きっと面白いと思う。正平氏もたぶんこの人選に異存はないだろう。
大著の翻訳(2年かかった)から解放されて、今は久々にゆったり、のんびりと静かにジャズを聴きたい気分なのだが、最近つくづくと感じるのは、配信、スマホ、SNS時代の今の世の中は何もかも慌ただしくて、余裕というものがない。映像は倍速視聴で楽しみ、Popsもコンピュータを使うせいだろうが、やたらとテンポの速い曲、コードチェンジ、リズムの複雑な曲、歌詞を目いっぱい詰め込んだような曲、ずっと声を張り上げて熱唱するような曲…と、とにかく「行間や余白、余韻の少ない」音楽が溢れている。作る側も聞く側も若い年齢層が中心なので、感覚的にそうなるのは当然でもある。だから趣味の音楽は、供給側任せにしないで、自分の好みや人生のテンポに合った音楽を、自分でセレクトして聞くようにしないと、年寄りには疲れて仕方がない。しかし今は、80年代シティポップや、カラオケで唄う若者にも昭和歌謡が人気のようで、それもよく分かる。現代の速い、複雑な音楽は疲れるし、微妙な感情の揺れや陰翳の表現とか、じわりと心に響くものが欠けているからだ。聴く人にとって分かりやすい、覚えやすい、唄いやすい、というのも音楽の魅力の重要な要素なのだ。ジャズも同じだ。たとえば漫画『Blue Giant』で描かれているような、血沸き肉躍るがごとき熱いジャズを聴き、かつそれを楽しむためには、聴き手側にも同じくらいの「エネルギー」を必要とするのである。主人公の宮本大だって、あんな熱量の高い演奏ばかりの音楽を続けていたら(…聞こえないが、想像で)、やがて身体がいくつあっても足らなくなるだろう。昔のジャズメンのドラッグ依存も、「同じことは二度とやらない=常に"創造"を求める」「演奏に全開の”パワー”を求める」という、ジャズ特有の要件(=脅迫観念)と大いに関係があるのだ。
 複雑化しすぎた現代の音楽が「分かりやすいメロディ」を失って久しいが、どんなに時代が変わっても、人間にとって美しいメロディは永遠だ。煎じ詰めたら「音楽の価値」とはそこにこそある。ビバップ以降、曲のテンポを上げて、コードで分解して音楽を複雑化し、さらにモードやフリーを経て、記憶に残るようなシンプルなメロディの美をポピュラー音楽から喪失させた責任の一端はジャズにあるのだろうが、そのジャズにも、モンクのように「コードなど忘れろ。メロディこそが大事だ」と、常にメロディを重視していた音楽家はいるし、幸いなことに、録音と共に歩んできた20世紀の音楽ジャズにはそうした演奏の記録も山ほど残されている。昔は盛んだった「ジャズ・ヴォーカル」が(私は今も好きだが)、ジャズにもあったシンプルで美しいメロディを、分かりやすく世の中的につなぎとめていたのだが、今はそうした曲が演奏され唄われる機会も減って、聴く人も減り、美しいメロディを持つジャズ演奏の「記憶」が世の中から失われつつあるのは残念なことだと思う。
複雑化しすぎた現代の音楽が「分かりやすいメロディ」を失って久しいが、どんなに時代が変わっても、人間にとって美しいメロディは永遠だ。煎じ詰めたら「音楽の価値」とはそこにこそある。ビバップ以降、曲のテンポを上げて、コードで分解して音楽を複雑化し、さらにモードやフリーを経て、記憶に残るようなシンプルなメロディの美をポピュラー音楽から喪失させた責任の一端はジャズにあるのだろうが、そのジャズにも、モンクのように「コードなど忘れろ。メロディこそが大事だ」と、常にメロディを重視していた音楽家はいるし、幸いなことに、録音と共に歩んできた20世紀の音楽ジャズにはそうした演奏の記録も山ほど残されている。昔は盛んだった「ジャズ・ヴォーカル」が(私は今も好きだが)、ジャズにもあったシンプルで美しいメロディを、分かりやすく世の中的につなぎとめていたのだが、今はそうした曲が演奏され唄われる機会も減って、聴く人も減り、美しいメロディを持つジャズ演奏の「記憶」が世の中から失われつつあるのは残念なことだと思う。2023/12/28
ジャズと翻訳(6)ソニー・ロリンズ
 |
| Saxophone Colossus Sonny Rollins (1956 Prestige) |
 |
| Saxophone Colossus by Aidan Levy (2022 Hachette Books) |
 |
| The Bridge Sonny Rollins (1962 RCA) |
.jpg) |
| "A Great Day in Harlem" by Art Kane (Aug.12, 1958) |
.jpg) |
| ロリンズ近影 |


.jpg)








