 |
| ヘル・パラダイス(2018年部分) |
 |
| スケッチング・スカイスクレーパーズ 2025年部分 作家蔵 |
 |
| I Thought About You A Tribute to Chet Baker Eliane Elias (2013) |
 |
| My Ideal A Tribute to Chet Baker Sings Amos Lee (2022) |
 |
| ヘル・パラダイス(2018年部分) |
 |
| スケッチング・スカイスクレーパーズ 2025年部分 作家蔵 |
 |
| I Thought About You A Tribute to Chet Baker Eliane Elias (2013) |
 |
| My Ideal A Tribute to Chet Baker Sings Amos Lee (2022) |
 |
| YouTube 動画 (shijimi) 藤圭子* 追悼:みだれ髪 |
私は単なるド素人のジャズ好きだが、この十年間はジャズ書の翻訳という仕事もあって、普段はほとんど作業BGMとしてジャズばかり聴いている(たまにあいみょん等も聴く)。このブログも、そもそもジャズを中心にした素人記事を好き勝手に書いて投稿してきたのだが、毎年、雪の便りが聞こえてくる季節になると、恒例のように、なぜかむずむずと急に演歌が聴きたくなる。そんな時、まず浮かぶのが「風雪ながれ旅」や「みだれ髪」など、船村徹 (1936-2017) の代表的名曲だ。2018年1月に、私は本ブログで「藤圭子『みだれ髪』の謎」という記事を書いている。YouTubeで見つけた動画での藤圭子の歌に感動して書いた記事である。この投稿は、200を超える8年間のジャズ中心の全ブログ記事のうち、今でも他の記事を大きく引き離す第2位のアクセス数に達している人気記事だ。今はSNS拡散の影響が強いので、ブログ記事へのアクセス層や数の実態は掴みにくいが、いずれにしても、この名曲と藤圭子の根強い人気に、あらためて感心している。
アメリカ南部発生の「ブルース」が、アメリカを代表する音楽であるジャズ、R&B、カントリー等の源流の一つであるように、歴史的に昭和の演歌・歌謡曲へと連なる日本の伝統的大衆歌は、いわば「日本のブルース」にあたるもので、各地の民謡や地唄、浪曲等の伝統を通じて古くから日本人のDNAに刻み込まれてきた音楽だ。特に昭和ひと桁から団塊にかけての世代には、幼少期にラジオやテレビを通じて無意識のうちに身体に浸み込んでいる音楽なので、私を含めて、演歌を聞くと今でもほぼ条件反射的にそのメロディに反応してしまう人が多いと思う。演歌には名曲も数多いが、中でも古賀政男と並んで船村徹は、日本的哀愁と抒情を強烈に感じさせる名曲をたくさん書いてきた作曲家だ。春日八郎の「別れの一本杉」とか「柿の木坂の家」など、流行歌として幼少期に自然に聞こえてきた曲は、今でもはっきりと記憶に残っている。特に「みだれ髪」のような歌詞(星野哲郎)、曲、双方ともに古風で格調高い名曲は、日本人の心の琴線に触れる何かがあるように思う。そしてジャンルに関わらず、昔からそうした名曲には、かならず興味深い背景や物語があるものだ。
.jfif) |
| 船村徹 |
 |
| YouTube 動画(man nabe) みだれ髪・17名歌手競演の歌い比べ (2021) |
美空ひばり 、田川寿美、水森かおり 、森昌子、石川さゆり、由紀さおり、藤圭子、天童よしみ、キム・ヨンジャ、 伍代夏子 、三沢あけみ 、藤あや子、船村徹、弦哲也、氷川きよし、五木ひろし、島津亜矢
 |
| 塩屋埼灯台 |
これまで聞いたことのない歌手もいるが、さすがにみなさん歌は上手で、また全員がそれぞれ個性的なので、聴く人の好みによるだろうと思うが、この曲は恋に破れた女性の心情を描いた歌なので、やはり女性歌手の方が似合うと思う。ただし、この曲の歌詞の意味は単純ではないので、歌唱は辛い思いと未練はもちろん、死を暗示する絶望まで滲ませて唄うべき曲だという解釈もあり得る。星野哲郎の歌詞は当初4番まであったそうで、ひばりの意見も入れて言葉を選択し、それを3番までにまとめたそうだ。だからこの曲は詞の解釈そのものがまず複雑であり、それを伝える歌唱技術、情感の表現技術も含めて、文字通りの難曲なのである。船村徹が「素人には…」と語った真意も、単に音域や唄い方の技術だけのことではなく、この歌の持つそうした深さをどう表現するかという点を指しているのではないかと思う。それをプロの歌手たちが、どうこなして歌として伝えているか、というのがこの曲の聴き比べの面白さだろう。
だが何度聴いても、結局のところ私の個人的印象はやはり7年前と変わらなかった。つまり本家の美空ひばりと、作者の船村徹を除けば、藤圭子の歌が圧倒的に素晴らしく、また心に響いてくるのである。この難曲を完全に「自分の歌」にしている、という以外に表現のしようがないが、「いかにも」な表面的な感情表現ではなく、歌詞の理解の深さと、心の底から絞り出すような寂寥感、情感の表現など、聴き手に訴えかけてくるものが違うのである。しかもその録画は、ほぼ休業状態だった90年代の藤圭子が、素人のような格好で、テレビのカラオケ番組で唄っている記録であり、決して正式な歌謡番組とか舞台上のパフォーマンスではないのだ。本当に、この藤圭子の歌には何度聴いても不思議な感動を覚えるし、私にとって依然としてそれは「謎」のままだ。7年前のブログにも書いたが、美空ひばりと藤圭子の歌は、どちらがうまいとかいうよりも、そもそも「歌の世界」が違うのだ。ただ一人、美空ひばりだけを歌手として尊敬している、と公言していた藤圭子のいわば "インフォーマル"で ソウルフルな歌唱が、「美空ひばりの名曲」の素晴らしさを、彼女の死後、奇跡的に「増幅した」とも言えるだろう。船村徹が藤圭子の唄うこの「みだれ髪」を聴いていたら、どんな感想を述べただろうか、と今でも思う(残念だが、その情報はない)。
 |
| YouTube動画 (miyakonoameni) 都の雨に |
"ブレイム・イット・オン・マイ・ユース Blame It on My Youth"は、1934年に作曲された古いバラード(曲 Oscar Levant、詞 Edward Heyman)。「あれも、これも、若さゆえの……」という歌詞で、タイトル通り、どう訳しても日本語なら『若気の至り』しかないだろう。誰しもそうかもしれないが、思い起こせば私も「若気の至り」が山ほどあって、入りたい穴がいくつあっても足りないくらいだ。しかし、人間若いころは本当にバカなことを言ったり、したりするものだと思う。反省するしかない(もう遅いが)。
 |
| After Midnight (1957) Nat King Cole |
 |
| The Cure (1990) Keith Jarret |
 |
| The Art of the Trio Vol 1 (1997) Brad Mehldau |
 |
| Minor Meeting (2001) Carsten Dahl |
 |
| Pao (2001) Eugene Pao |
あいみょんは作曲するとき、ギターを弾いて唄いながら歌詞とメロディを「同時に」作ってゆくらしい。ギターコードもそれほど知識はないのだという。だからシンプルなコードとその進行と同時に、歌詞とメロディが無理なくごく自然につながっていて、どの曲も妙な飛躍やひっかかりがなく、「歌」がストレートにこちらに訴えかけてくる。大半の作品で、曲全体の構成の「起承転結」が明瞭で、ゆっくりとした独り言のような低域の導入部から徐々に盛り上げて高域側へと移行し、記憶に残るキャッチーなサビのメロディが必ずあり、最後も絶叫や、静かに落として終える、という安定したパターンが多い。また一部のラップ的な曲を除けば、テンポ(bpm)もゆったりした曲が多く、多少テンポが上がっても、発声がクリアなので歌詞やメロディが聴き取りやすく、かつ覚えやすい。だから聞き終わったあと、かならず歌詞とメロディが頭の中に何度も繰り返し浮かんで来る。最低5回は聴かないと(?)何を言っているのかさっぱり分からない歌詞と(歌詞が分かっても意味が分からない…)、メロディも覚えにくい最近の他の歌とはそこが違う。世代、年齢を超えて人気があり、特に中高年層にも人気があるのは、メロディ自体の魅力に加え、こうした伝統的な日本のポップス(大衆曲)の基本を備えているからだろう。そこに1970-80年代の日本のポップス黄金期の香りが加わっているので、どの曲も中高年にとっては懐かしく、抵抗なく覚えられ、自分でも「唄ってみたい」という気にさえなるのだ。ライヴ会場での「君はロックを聴かない」のように、大ホールの大観衆が一緒になって唄えるような楽曲は最近聴いたことがなかった。しかも単なるその場のノリだけではなく、会場全体に、聴衆の「この歌への共感」が溢れているところがすごい。感動的ですらある。
椎名林檎は、ユーミンが全盛期だった高度成長下1978年に生まれた団塊ジュニア世代、あいみょんはその椎名林檎が登場した時代、バブル崩壊後の不況下1995年という阪神大震災の年に生まれた世代だ。その後 9.11、リーマン、東日本大震災、コロナという厄災を経て日本経済が完全失速した「失われた30年」という時代を生きて来た。アーティストの作品が、音楽家としての個々の音楽性以外に、それぞれの世代の経験と、生きた時代の空気を映し出すのは当然だ。そしてそれは、後の時代になって振り返って見えて来るものだ。たとえばユーミンは「70年代的希望」、椎名林檎は「90年代的挫折」だったように思うが、あいみょんはどうなるだろうか。時代の空気は「沈滞とあきらめ」だが、あいみょんの音楽には、その時代背景から生まれる肩の力が抜けたクールネスと、逆境をバネにして反発するくじけない姿勢、かすかな希望が常に感じられる。つまり時代はネガティヴだが、彼女の音楽そのものは超ポジティヴなのだ。英語にheartful(心のこもった)とencourage(勇気づける)という単語があるが、あいみょんの歌にはheartfulな温かさと、聴き手をencourageするパワーが常に感じられるのである。だから聴くと元気が出る(私のような年寄りでさえも)。そこが彼女の音楽のいちばんの魅力であり、5年近い「コロナの鬱」を乗り切るのに、あいみょんの歌は日本中に癒しと力を与えたと思う。私の世代にとって明るい1970/80年代の音楽がそうだったように、あいみょんと同世代の若者にとっては、きっと生涯忘れられない音楽になることだろう。あいみょんはギターコードもその進行も、それほど詳しくなくて、あくまで浮かんでくるメロディライン優先の作曲のようだ。「マリーゴールド」や「愛を伝えたいだとか」が何かのパクリだとかいう説が、ネットの一部で取り上げられているが、最近ポップスの定型コード進行と、メロディの近似についてやたらと吹聴する人間が多い。だが、そんなことを言い出したら、ジャズなどどうなるのか…という話だ。メロディとコード進行に基づく即興演奏(変奏)がジャズの基本なので、同じコード進行を基にしたメロディなどいくらでもできる。だから、そのジャズを片親にした洋楽(ロック、ポップス)など昔から、いわばパクりのオンパレードだ。12音を使ったメロディは無限に作れるはずだが、コード解析が進んだ21世紀の今はもう出尽くした感があるのと、1990年代以降のデジタル音楽時代になってから、20世紀の人間が個人として持っていた素朴な音楽的感性と創造力が、世界的に衰えてしまったのではないかと私は思っている。昔からポップスにはクラシックのカノン進行など、近代の人間が「心地よく感じる和声の動き」を応用した例がたくさんあるのは事実だ。しかし、その和声を基にして本当に素晴らしい「メロディ」を新たに生み出す才能はまた別なのである。人を気持ちよく感じさせるそうしたコード進行は、料理にたとえれば「上質な出汁(だし、スープ)」みたいなものだ。その出汁を使って、「うまい料理」をいかに作るかは、料理人の創造力と腕なのだ。あいみょんの音楽には、そういう出汁をベースにしながらも、どの曲にも名料理人的な確かな腕と、発想のオリジナリティを感じる。そして味を仕上げるリズムとメロディの引き出しが多彩で、しかも、完成した料理の味は大多数の人が好むものだ。1曲や2曲だけならまだしも、味付けの異なる上質な曲を何十曲も創作する彼女の才能は本当にすごいと思う。「おいしい街の洋食屋さん」という所以である。
あいみょんのもう一つの個性は地域性だ。関西人だが、ど真ん中の大阪ではなく神戸に近い西宮市出身なのでアクは強くない。だが当然ながらネイティヴ関西女子特有のユーモアとウィットがあり、ラジオの『オールナイトニッポンGOLD』を聞けば分かるように、喋りも明るく、親しみやすく、何と言ってもとにかく面白い。コンサートで客席と楽しくやり取りするMCぶり、エンタテイナーぶりも素晴らしい。しかし一方で、路上ミュージシャン時代からグループに属さず、ギター一本で自分の道を独りで切り拓いてきた「孤高の人」が持つ体育会系の強靭さも感じる(映像で見ても、ライヴのステージ上ではすごいオーラを感じさせる)。人格は(想像だが)、潔く、さっぱりしていて男前、ストイックかつ真面目で、常に冷静に自分のことを見ている。年上、先輩の人たちに対する態度も控え目で、礼儀正しい。幸福な家庭で育ったことを伺わせるように、両親や家族への愛を、常におおらかにあけっぴろげに語っているところも関西人らしい。彼女に直接会った年長の芸能人たちがみなファンになるのは、曲もさることながら、こうした礼儀正しさと、バリアを感じさせない、おおらかな関西風キャラのせいだろう。というわけで、今さらながらの私的感想だが、あいみょんは「女性シンガーソングライター」として、間違いなく1970年代のユーミン、中島みゆき、1990年代の椎名林檎、宇多田ヒカルに続く才能だと思う。ちなみに今の私(後期高齢者)の愛聴曲は……特に独自の選曲はなく全部気に入っているが、中でも特に好きなのは「ハルノヒ」「愛を伝えたいだとか」「君はロックを聴かない」「今夜このまま」「ラッキーカラー」「あのね」…等々だ。椎名林檎と同じで、こうした名曲群をほぼ20代前半までに作っているところもすごい。椎名林檎は、サブカル的あぶない少女歌手のイメージから、セクシーでゴージャスな大人の女性アーティストへと変身していったが、今年30歳になったあいみょんが、音楽家として今後どういう道を歩んで行くのか興味深い。個人的希望を言えば、ありきたりのデジタル音楽やAIに負けず、今の手作り的、アナログ的で、シンプルでストレートというオリジナルな音楽世界を、今後もアコギで追及していって欲しいと思う。
 |
| Misty 山本剛 (1974) |
.jfif) |
| The Original Misty Errol Garner (1954) |
 |
| Vaughan and Violins Sarah Vaughan (1959) |
 |
| Smokin' at the Half Note Wes Montgomery (1964) |
 |
| Flamingo S.Grappelli & M.Petrucciani (1995) |
"フォー・オール・ウィ・ノウ For All We Know" は、1934年に書かれた古い曲で (J. Fred Coots曲/ Sam M. Lewis詞)、短く、どちらかと言えば歌詞もメロディも地味だが、別れゆく男女の、やむにやまれぬ切ない気持ちが込められた非常に美しいラヴソングである(70年代にカーペンターズが唄ったのは同名異曲)。だが単に陳腐でセンチメンタルな恋歌ではなく、曲に品格があり、いかにもアメリカン・バラード的な温かさ、やさしさが歌詞とメロディ全体から伝わってくる名曲だ。だから唄い上げるよりも、哀切さと共に、歌の底に流れる、相手を思いやるやさしさが、さりげなく表現されている穏やかな歌唱や演奏が曲想に合っていると思う。『Lady in Satin』(1958) のビリー・ホリデイBillie Holiday の歌唱はこの点でまさに完璧だ。
 |
| Lady in Satin Billie Holiday (1958) |
私有の女性ジャズ・ヴォーカルでは、ニーナ・シモン (1957)、とドーリー・ベイカー(1993)があるし、男声ではナット・キング・コール (1958) も有名だ。しかし上述した理由から、ゴスペル調でドラマチックに唄い上げるニーナ・シモンや、高らかな美声のナット・キング・コールよりも、最晩年(亡くなる前年)、人生を知り尽くし、彼岸に向かって歩き始めたかのように、ストリングスをバックに仄かな暗さを湛えて唄う『Lady in Satin』のビリー・ホリデイの枯れた歌唱が、私的にはやはりいちばん心に響く。声や技術の衰えとか、年齢による歌唱の質の問題はあるだろうが、そんなことなど超越した、歌に込めた情感の素晴らしさがこのアルバムのホリデイにはある(それは、バド・パウエルやモンクといったジャズの巨人たちの、最晩年の演奏にも感じることだ。)"I'm a Fool to Want You" をはじめ、 ホリデイのこのレコードは全曲が素晴らしいが、特にこの曲は短く、シンプルで、美しいがゆえに、なおさらだ。
 |
| The Art of the Trio Vol.3 Brad Mehldau (1998) |
.jpg) |
| Jasmine Keith Jarret & Charlie Haden(2010) |
 |
| Guitar On the Go Wes Montgomery (1961) |
 |
| Live in Tokyo Chet Baker (1987 King) |
この1-2年、腰の調子が悪く、都心へ出かけることもほとんどないので、東京都心の風景の変貌ぶりに驚いたが、もっと驚いたのはコンサートの客層だ。普通のジャズ・ライヴやコンサートではおよそ見かけない、若い観客、特に女性が多いのにびっくりした。私がこれまで出かけたジャズ・コンサートでは、中高年層、それもたぶん60代以上の人たち(ほとんどオッサン)が大半で、平均年齢も60から70歳くらいだった。今回は、満員(2000人?)の客層が老若男女万遍なくいることが何より驚きだった。都心の変貌と言い、まるで浦島太郎になったような気がした。コロナを境に(年寄りが減って) 客層が変わったということなのだろうか? 全体としてジャズ人気が高まったわけでもないだろうし、やはり「現役」メルドーの人気を反映しているのだろう。30年前の90年代キース・ジャレットの来日コンサートを思い出した。ビル・エヴァンス(70年代)→ジャレット→メルドー…と、特に女性は、やはりジャズと言えば白人ピアニストなのだと改めて実感した。
それとメルドーはクラシックの影響も濃く、しかもプログレッシヴ・ロック(プログレ)にも並々ならぬ愛着を抱いているので、普通のジャズ・ファンに加えて、クラシック・ファン、ロック・ファン層も相当来場していたと思われる。今回のトリオは東京で計4回(オペラシティ、紀尾井ホール2回、サントリーホール)、大阪(サンケイホール)で1回と、1週間で都合5回のコンサートをほぼ1000人以上収容の大ホールで開いたわけで、単純計算でもそれだけで五千人以上の観客を動員したことになる。1日で万単位のロックやポップスには到底及ばないが、ジャズでこの観客動員は異例だろう。まさに21世紀の多様性を象徴するジャズ界のスター、メルドーならではということだろう。5回のコンサート演目は後に発表された資料によると、各回9ー10曲だが、重複は数曲しかないので、このトリオは計50曲前後のレパートリーを準備していたことになる。
実は私はメルドーの「大ファン」とは言えない。90年代後半の初期のトリオ以降、出るCDはそこそこ購入してきたが、どうもこれまでロクに(真剣に)聴いて来なかったからだ。理由はおそらく、彼のバンドの特徴である独特のリズム(変拍子、複合拍子)のゆえに、メロディ重視のバラード曲を除くと、少なくともレコードでは20世紀のジャズ的グルーヴ、ジャズ的カタルシスがあまり感じられないからだった。クラシックも人並みには聴いているが、ファンというほどでもないし、ロック・ファンでもないし、当然プログレの特徴もよく知らないので、演奏の中に共感できる部分が少ないからだろう。総体としては、ウェイン・ショーターのモダンなサックスを聴いたときに感じたものと似ている。斬新で、すごいとは思うのだが、どうも没頭して聴く気が起きないのだ。やはり20世紀半ばのビバップ系モダン・ジャズ体験がデフォルトなので、少なくとも前進するリズムのメリハリが欲しいのだろう。とはいえ、今回のコンサートは久しぶりのライヴということもあって、もちろん楽しんだ。
「サントリーホール」のコンサートの演目(左表)で、いちばん気に入った曲は3曲目の "#26" という、メルドーのオリジナル曲だ。#26の意味はよくわからないし、まだ名前がない曲なのか?と思って調べたら、『Ode』(2012)というアルバムに収録されていた。曲の中盤で高速インプロに入ってからのトリオの疾走感は素晴らしかった。これはレコードでは決して味わえない快感で、ハイウェイ上を「地を這うように」疾走するかのような、重心の低い高速サウンドには興奮した。バラード以外のメルドーの演奏で初めてグッときた曲で、なるほどこういう魅力もあるのだと感心した。"East of the Sun" "The Nearness of You" などのジャズ・スタンダードは普通に楽しめた。アンコールでやったモンクの "Think of One" も意外で、よかった。
特に大ホールでのジャズのライヴ・コンサートというのは「夢」と似ている。聴いているときは結構盛り上がって、感激することもあるのだが、終わって時間が経つにつれて、いったい具体的に演奏のどこが、何が良かったのかよく覚えていないことが多いからだ。ライヴ録音CDなどを冷静に聴いていると、演奏後の聴衆の熱狂ぶりに「どこがそんなに良かったんだ?」と、思わず突っ込みたくなるようなケースが時どきあるが、あれも同時体験という現場の空気が生むものだろう。サウンドと時間が同時に流れているので、その最中には忘我の状態にすらなれるが、逆に後で思い出そうとしてもその流れそのものが思いだせないこともある。これは私が大雑把な人間なのと、多分歳のせいもあるが、ジャズの場合演奏する曲も、クラシックやポップスのように曲名がすぐに分かるとは限らないし、演奏自体もその場で生まれる即興演奏であり、音楽として複雑なので、素人は細部の記憶が曖昧になることが多い。それにレコードと異なり、ライヴの場合、見た目(ヴィジュアル情報)とサウンド両方を、同時に脳が追いかけて処理するので、メモリー上はインパクトが強いヴィジュアル情報が勝って、サウンド側の記憶が相対的に弱くなる。だから当日のステージ上の映像イメージは鮮明でも、演奏そのものの記憶が相対的に薄まるのではないか、という気がする。
 昔のジャズファンは、いまほど潤沢に本物のサウンドに触れる機会もなかったので、それこそ真剣に「音そのもの」と対峙して聴いていた。あの1960/70年代のジャズ喫茶時代を生きた平岡正明氏などは、「ジャズは生がいちばんだが、ライヴは演奏している人間が邪魔、家で聴くと自分が邪魔だ。だからジャズ喫茶で聴け」という、名言(?)を残しているほどだ。だが普通の聴き手にとっては、ジャズのライヴ演奏はやはり、その場でパフォーマンス自体を楽しむもので、音や演奏内容の細部をあれこれ云々する場ではないのだろう。昔の山下洋輔Gのフリー・ジャズなどはその典型で、今でもサウンドを含めた「身体経験」として記憶している。これは観衆も受け身ではなく、奏者と共に場を構成するメンバーの一員だという意味でもあり、元々ロック・コンサートなどはまさにそういう場になっているが、日本の普通のジャズ・ライヴの場合、なかなかそこまで盛り上がるケースは少ないだろう。どうしても分析的に(頭で)聴く傾向が強いのが日本の伝統的ジャズファンで、そこがまたジャズの魅力でもあると思うのだが、今回のメルドーはそういう意味でも「観客」の反応がいつもと違い、スタンディング・オベーションもごく普通に自然に起きていた。
昔のジャズファンは、いまほど潤沢に本物のサウンドに触れる機会もなかったので、それこそ真剣に「音そのもの」と対峙して聴いていた。あの1960/70年代のジャズ喫茶時代を生きた平岡正明氏などは、「ジャズは生がいちばんだが、ライヴは演奏している人間が邪魔、家で聴くと自分が邪魔だ。だからジャズ喫茶で聴け」という、名言(?)を残しているほどだ。だが普通の聴き手にとっては、ジャズのライヴ演奏はやはり、その場でパフォーマンス自体を楽しむもので、音や演奏内容の細部をあれこれ云々する場ではないのだろう。昔の山下洋輔Gのフリー・ジャズなどはその典型で、今でもサウンドを含めた「身体経験」として記憶している。これは観衆も受け身ではなく、奏者と共に場を構成するメンバーの一員だという意味でもあり、元々ロック・コンサートなどはまさにそういう場になっているが、日本の普通のジャズ・ライヴの場合、なかなかそこまで盛り上がるケースは少ないだろう。どうしても分析的に(頭で)聴く傾向が強いのが日本の伝統的ジャズファンで、そこがまたジャズの魅力でもあると思うのだが、今回のメルドーはそういう意味でも「観客」の反応がいつもと違い、スタンディング・オベーションもごく普通に自然に起きていた。
 |
| Mating Call Dameron/Coltrane (1957 Prestige) |
 |
| Plays Tadd Dameron Barry Harris (1975 Xanadu) |
 |
| Gentle November Kazunori Takeda (1979 Frasco) |
 |
| Playin' Plain Koichi Hiroki (1996 Biyuya) |
『鑓の権三』の原作は、近松門左衛門の世話物・人形浄瑠璃『鑓の権三重帷子(やりのごんざ・かさねかたびら)』(1717年初演)で、これは『心中天網島』より3年早い作品だ。篠田監督としては、岩下志麻と中村吉右衛門を起用した『心中天網島』(1969年表現社/ATG)に次ぐ近松もので、スタッフも富岡多恵子(脚本)、武満徹/琵琶・鶴田錦史(音楽)、粟津潔(美術)と『天網島』と同じで、『天網島』が成島東一郎のモノクロ、『権三』が宮川一夫のカラーという撮影(カメラ)だけが違う。主役「鑓の(笹野)権三」は郷ひろみで、火野正平、田中美佐子に加えて岩下志麻、大滝秀治、河原崎長一郎、加藤治子などそうそうたる俳優が出演している。
『天網島』もそうだが、『権三』も享保時代の実話を元にして、近松が書き下ろした作品。実際の事件は、松江・松平家の茶道役・正井宗味が江戸詰中に、小姓役・池田文次(24歳)が妻のとよ(36歳)と密通し、享保2年(1717年)6月に駆け落ちした。正井が二人を追跡し、7月に大坂高麗橋上で「妻敵討」(めがたきうち:姦通相手の男を殺すことは公認されていた)したというもの。翌8月には、近松の作品を竹本座で初演したというから、デジタル時代も顔負けのものすごいスピード制作と上演だ。
原作は実話に沿い、映画も『天網島』と同様、ほぼ近松の原作に沿って作られている。戦のない開幕後100余年間に、武士の出世競争もすっかり様変わりして、武芸のうち茶道もその有力な要素となっていた。出雲の国・松江藩を舞台に、鑓の名手で、茶道にも通じ、しかも城下の俗謡で唄われるほど美男子で有名だった「笹野権三」を郷ひろみが演じ、出世争いのライバルだった「川側伴之丞」(かわづらばんのじょう)を火野正平が、その妹で、兄に内緒で権三と言い交わしていた「お雪」役を田中美佐子が演じている。権三と伴之丞の茶道の師で、松江藩の茶道の筆頭師範・浅香市之進(津村隆)が藩主と共に江戸詰の留守中であり、藩主の世継ぎ誕生を祝う殿中饗応の席で披露する「真の台子(だいす)」という最高峰の茶の作法を弟子の誰かに努めさせよと指示し、市之進の妻おさゐ(おさい、岩下志麻)を仲立ちに、その役目と秘伝の伝授を巡って郷と火野が争う。一方、女として権三に惹かれていたおさゐは、伴之丞(火野)から何度も色仕掛けで迫られていたが断り続けていた。だが自分の娘を権三がめとれば秘伝も家中のものとして自然に授与できると考えていた。印象に残ったのは、モノクロの『心中天網島』では、ほとんどがスタジオ内での制作で、屋外ロケは最後の道行場面だけだったのに対し、『権三』では、各地のロケ(出雲、松江、萩、彦根、奈良、京都、岩国…)を含めて、絵葉書のような美しいカラー映像と豪華な衣装美がこれでもか、と続くことで、鑑賞上これは文句ない。ロケだけでも大変なコストがかかっただろうが、これはバブル期ならではだろう。また乗馬シーンでの郷ひろみの馬さばきも見事だ。ダンスもそうだが、この人は本当に運動神経がいいのだと思う。ただし美男を強調するために、眉を含めて「化粧」が濃すぎではないか?(火野正平がよけいにウスく見えてしまう)。海岸を馬で走るシーンはおそらく萩の菊ヶ浜で、田中美佐子が先週くらいの「こころ旅山口編」で訪れていたはずだが、番組中では特にコメントはなかった。
当時40代の岩下志麻は容姿、所作、台詞ともに相変わらずの美しさで(監督もそこだけは手抜きがない…どころか一番力が入っている)、夫の留守を守るその岩下志麻に言い寄る火野正平の女好きぶりは、まあお約束かもしれないが、ライバルの権三には嫁がせまいと反対しつつ、自分の妹にまであわや手を出そうとするあぶないシーンがある。あれは台本なのか、アドリブなのか、演技の勢いなのか? あげく、二人の密通(濡れ衣)を城下に言いふらしたために、最後はおさゐの兄(河原崎長一郎)に討たれて、生首(これがよくできている?)になって戻ってくる。火野正平は侍よりも、やはりひとクセある町人とかワル役が似合いそうだが、正平氏自身は『権三』の役どころをどう思っていたのだろうか? 田中美佐子はたまたまこの映画の舞台だった(隠岐の島生まれ)松江が出身だそうで、40年前(20代半ば)は当然若くてきれいだが、郷ひろみとの濡れ場での大胆な演技には驚いた。それと竹中直人がちょい役で出ていたが、いつものギャグがなくて残念だった。
『心中天網島』は、いわば市井の商人と遊女の不義の物語で、ある意味普遍的なテーマなので、義理人情の部分を含めて、まだ現代人にも分からないことはない。だが『鑓の権三』は戦のない日本の武家社会が舞台で、しかも茶道の伝統とその価値がわからないと皆目話の道筋が見えない……2回見てやっとある程度理解したくらいだ。相当の予備知識がないと、話の筋も面白さも分からないだろう。この映画はベルリン国際映画祭で「銀熊賞」を受賞したそうだが、日本人ですらよく分からない、この大昔、封建時代の日本的価値観と倫理(論理)を、本当に西洋人が映画を観て分かるものなのだろうか? おそらく映像から見えて来る侍と日本的情緒、その美が、選考の一番の理由ではないかという気がする。1969年の『心中天網島』は、リアルタイムで観たせいもあって、私は心底感動して何度も観た。ほぼ同じスタッフで制作した17年後の本作と何が違うのか、考えてみたが、やはり時代だろう。1969年の日本は高度成長下とはいえまだ貧しく、全共闘運動をはじめ社会は騒然として緊張感が高かったが、一方で、不確かとはいえ、まだ「未来」に対する希望もあった。戦後生まれの世代が20歳を過ぎ、そのエネルギーが音楽や映画など芸術の世界でも爆発的な勢いで創造的な作品を生んでいた。そうした社会状況の下で、ほぼ全員30代の若いスタッフが、制作資金の制約のために、あえてミニマルな表現を目指した実験的な構成、展開と、モノクロによる映像を駆使した『天網島』からは、若さと熱意と創意、芸術性があふれている。一方、高度成長後の熟れ切った日本のバブル最盛期に、功成り名を遂げたスタッフが、たっぷり金と時間をかけて制作したエンタメ的なこの映画の質と出来は、やはり前作とは比較にならない。『天網島』から17年後の日本は豊かになったが、映画を取り巻く状況も変化していたし、69年の制作者たちが持っていたエネルギー、渇望、表現意欲…そういうものも間違いなく変貌していただろう。
ただし、火野正平と田中美佐子が、この映画の兄妹役を通じて親しくなったことはよく分かった。再スタート後1ヶ月を過ぎた今は、もう完全に田中美佐子の「こころ旅」になっているが、自転車で毎朝出発する時に、空に向かって「行ってきまーす!」と、手を挙げて明るく大声で叫ぶ田中美佐子の「兄」火野正平への挨拶がとてもいい。従来からの撮影スタッフも、やさしく彼女を支えているのがよく分かる。春に続いて「秋の旅」も田中美佐子がやることが決まったようでよかった。火野ー田中と「兄妹バトン」でつないだこの番組が、今後も長く続くことを願っている。(ただし、いくら電動アシストでも、65歳の女性に長い山登りルートはきつすぎる。難しいだろうが、ほどほどにしておかないと、正平氏のように腰を痛めますよ。)
 |
| Clap Hands, Here Comes Charlie! Ella Fitzgerald (1961 Verve) |
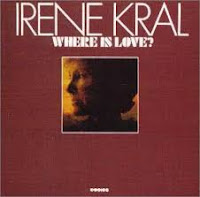 |
| Where is Love? Irene Kral (1975 Choice) |
 |
| Pop Pop Rickie Lee Jones (1991 Geffen) |
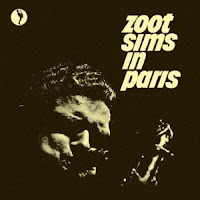 |
| Zoot Sims in Paris (1961 UA) |